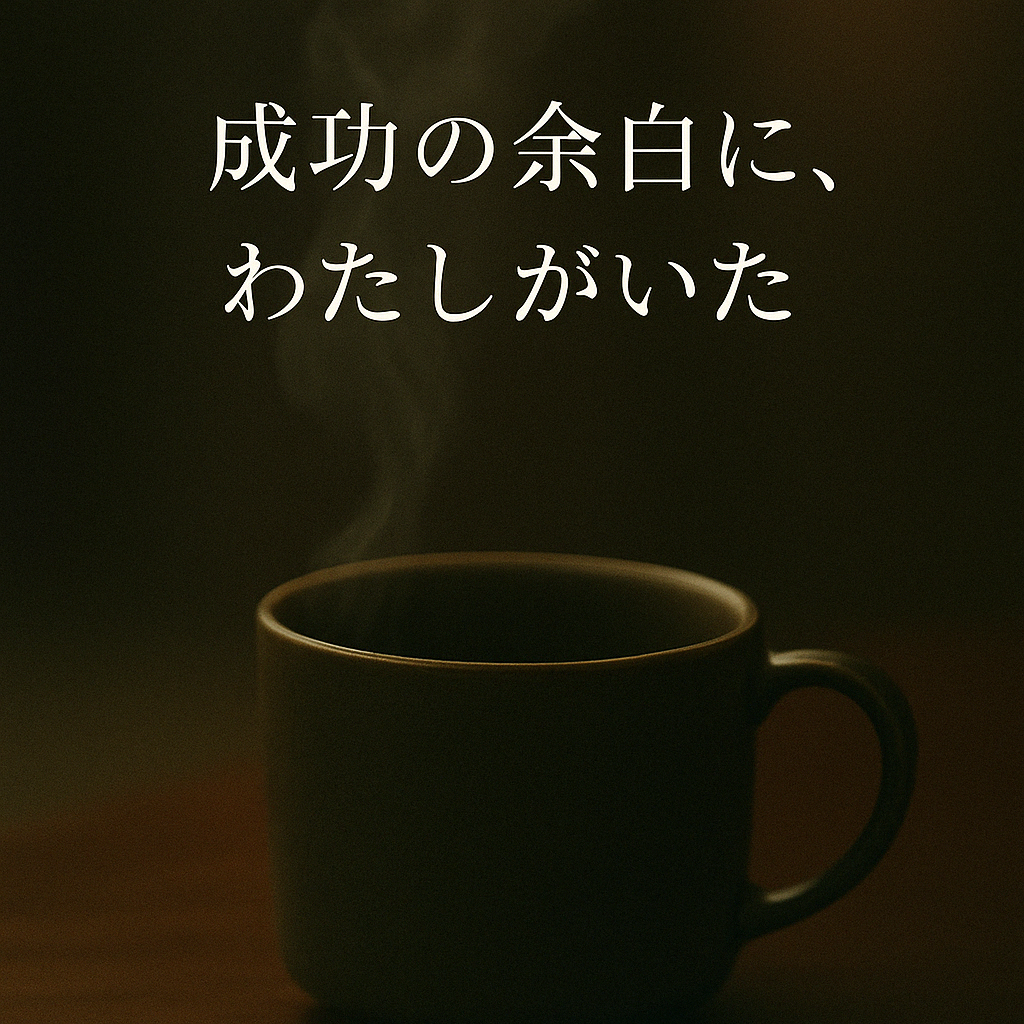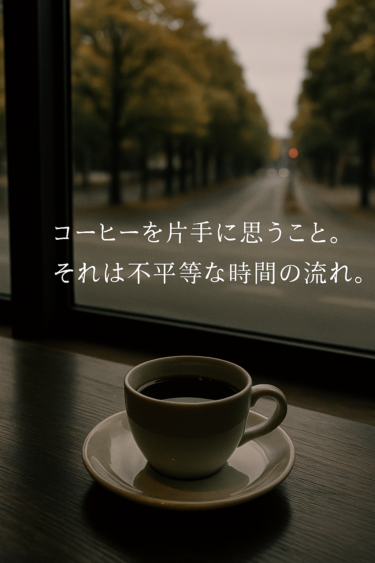──音無 Fade
いつもなら、ベランダでコーヒーを片手に
遠くのビルをぼんやり眺めている時間だった。
でもその朝は、雨が静かに降っていた。
トーストをかじりながら新聞をめくっていると、
携帯が震えた。
無意識に取る。
「……はい」
『あ、もしもし』
少しだけ懐かしい声だった。
けれど、懐かしさは罪に似ている。
『昨日のこと、なんだけどさ――』
彼女は笑っていた。あの頃と変わらない調子で。
―――あたし、好きな人がいるんだよねぇ。
その言葉が、昨日の夜、確かに落ちていた。
たぶん僕に向けたものじゃなかった。
それでも少しだけ、嬉しかった。
自分がその誰かじゃないことに、気づいていたのに。
報いだ。
僕は誰かの好意を雑に扱って、
なのにまた、別の人を好きになった。
そんな資格、ないとわかってた。
なのに、どうしてこんなにも苦しかったんだろう。
–
いつもと同じ昼休み。
仕事に文句はない。でも心はずっと騒がしいままだった。
誰もいないはずの屋上。
そこに彼女がいた。
静かにページをめくっていた。
僕は隣に座った。何も言えなかった。
彼女が本を閉じたのは、
僕が何も言わなかったせいかもしれない。
「知ってる? 人の心の中には天使と悪魔がいるのよ」
その言葉は、誰かにというより、
自分に言い聞かせるような声音だった。
「どっちも自分のことしか考えてない。
片方は愛を育みたいと願い、もう片方は快楽を求める。
だから、どちらも否定しなくていい。
でも――
その選択に後悔しない覚悟があるなら、の話だけど」
それだけ言うと、彼女は風のように立ち去った。
僕は何も言えなかった。ただ、彼女の後ろ姿を目で追っていた。
–
あれから数日。
駅に向かう道すがら、彼女の姿を見つけた瞬間、
心臓が跳ねた。
まさか――そんな偶然あるわけない。
けれど、現実だった。
彼女が僕の腕を掴んで振り返ったその瞬間、
あの日の沈黙すら愛しく思えた。
無言のまま電車に乗り、
密着した体温と、微かな香り。
記憶をくすぐるその空気に、息を殺すしかなかった。
–
街を歩きながらも、
彼女は何も言わなかった。
ただ少し楽しげに、前を歩いていた。
交差点の前で信号を待つあいだ、
彼女がふと立ち止まる。
振り向いたその瞳に、
僕は言葉を失った。
そして――
そっと指先が頬に触れ、
続いて、唇が重なった。
ほんの一瞬の、
だけど永遠にも感じられた時間。
「キス、しちゃったね」
その笑顔は、
まるで天使の仮面をかぶった悪魔だった。
–
「ねぇ、知ってる? 人の心には天使と悪魔がいるのよ」
彼女は続けた。かすれた声で。
「あなたが好きなの。
もし、あなたが私を好きじゃないなら――
私はあなたの心に棲みつく。
消えない夢みたいに。
だって……あなたが好きなんですもの」
–
あの雨の日から、
何もかもが少しだけ歪んで見える。
彼女の声も、笑顔も、
まるで“後悔”が作った幻想のようで。
だけど、
確かに今も、どこかに“棲みついて”いる。