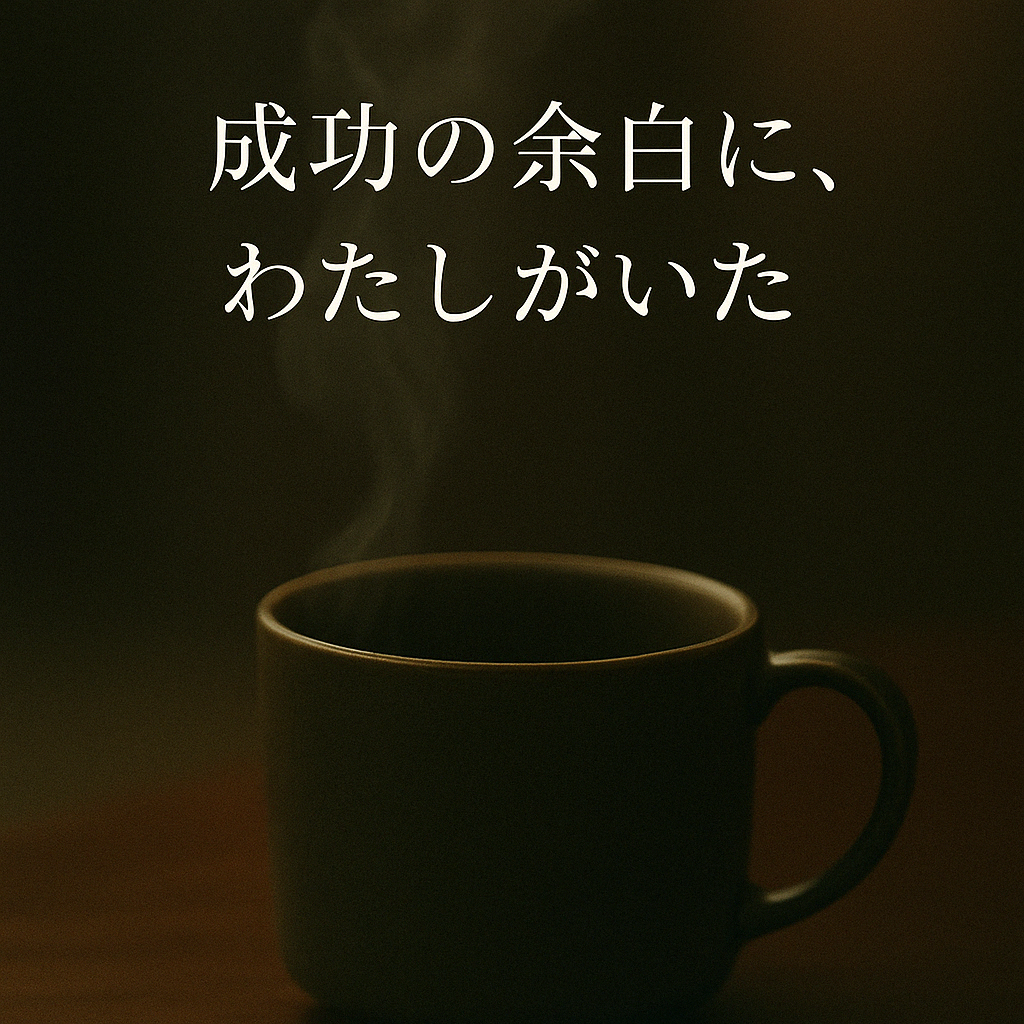── 音無 Fade
燃焼時にどうしても煙が出てしまう。
それは仕方のないことなのに、
いつも私は、その煙が目に沁みる理由を探していた。
使いかけのマッチの匂い。
夜のコンビニで買ったライター。
誰かの口癖みたいに、
その行為だけが、時間を止めてくれた気がしていた。
–
あの部屋には灰皿があった。
丸くて重たい陶器製で、
底にはいつも吸い殻と、私の言葉にならなかった感情が溜まっていた。
「煙たいね」ってあなたが笑ったあの日。
私たちの間には、もうすでに
“終わり”の匂いが漂っていたのかもしれない。
–
最後の夜、
私は一本の煙草に火をつけて、
なにかを燃やすように深く吸い込んだ。
でも、燃やせたのはタバコだけだった。
心の中の未練は、少しも減らなかった。
煙は黙って、部屋の天井に向かって伸びていく。
まるで、誰にも届かない手紙のように。
–
今はもう吸っていない。
でも、あの時の煙だけは、
ふとした瞬間に思い出す。
煙は、嘘をつけない。
いつだって、
何かを燃やした証として、空気の中に残る。
燃えかすだけを残して。
だから私は今も、
あの煙の向こうに言えなかった言葉を
見送ったままでいる。