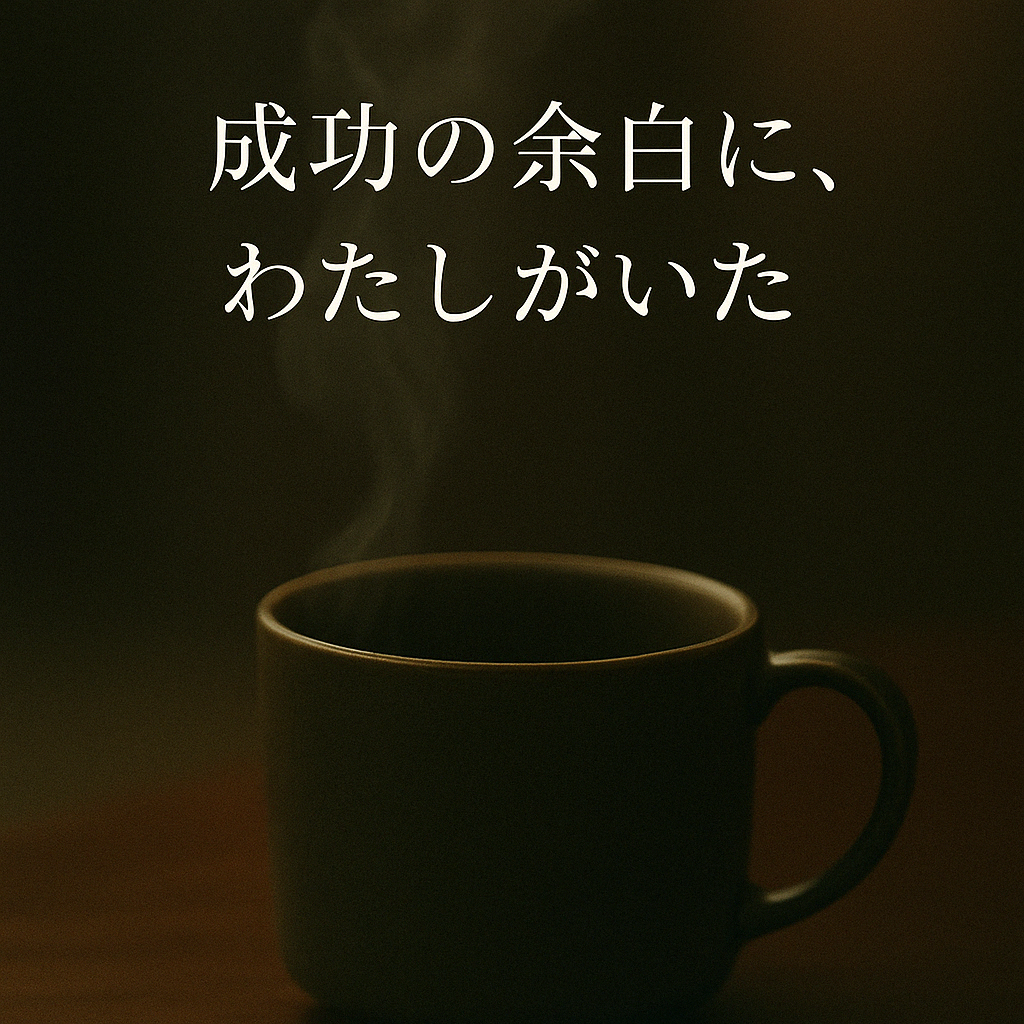音無Fade
雨音が消えてから、
この部屋はようやく、朝を迎えた。
目覚ましも鳴らず、誰の声も届かない午前。
雨が降っているのか、それとも昨夜の湿り気が残っているだけなのか、よくわからない。
ただ、窓の外はほんの少しだけ、
滲んでいた。
コーヒーを淹れる気にもならず、
テーブルの上には昨日のカップが置き去りのままだ。
飲みかけではない。飲むのを忘れていたわけでもない。
ただ、そうする意味が見当たらなかっただけだ。
遠くで、誰かの暮らしのドアが閉まる音がした。
その音だけが現実の証のようで、
こちらの時間はまるで、
ふと通り過ぎた夢の中に取り残されたようだった。
窓辺に立ってみる。
ガラスの向こうでは、誰かが傘をさしながら歩いている。
その姿を、ぼんやりと眺めていた。
知らない人だ。けれど、どこかで見たような気もする。
こんな曖昧な既視感ばかりが、
今日という日の輪郭を形づくっている。
机の端には読みかけの本。
しおり代わりに挟んだ紙片が、ページのあいだからわずかに顔を出している。
けれど、続きを読む気にはならなかった。
あの物語の主人公が、
この静けさの中では少しうるさすぎるような気がしたからだ。
名を呼ばれることのない朝。
こちらからも、名を呼ぶ相手がいない。
名前を口にすることが、
その人の不在を証明してしまう気がして、
言葉を飲み込む。
それでも、ふいに。
胸の奥から、ひとつの音が立ち上がった。
それはたぶん、
もう戻らないものに手を伸ばしかけた瞬間、
触れることを諦めた指先が、
わずかに空を揺らしたときの、音だったのだと思う。
誰にも聞こえない、
小さな余韻。
そしてその静けさのなかに、
確かに今日という一日が、
滲みはじめていた。