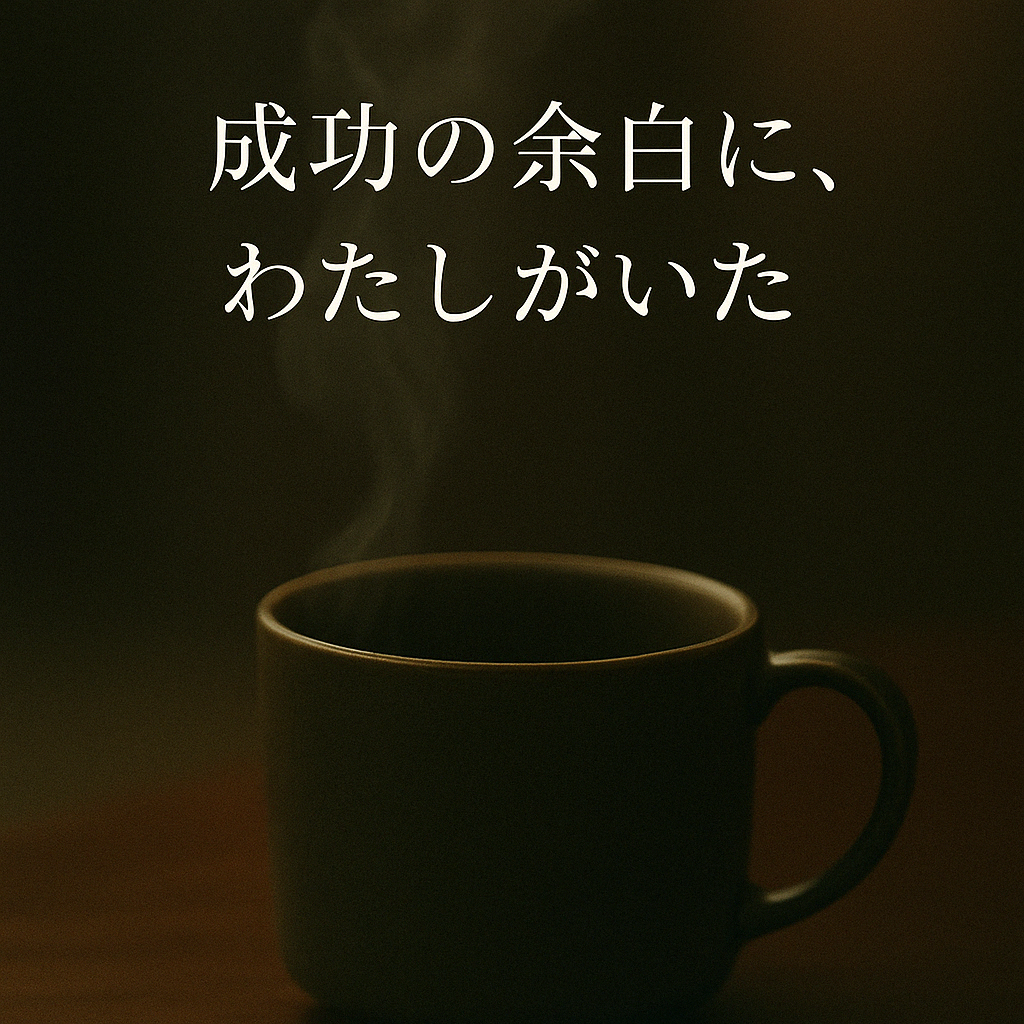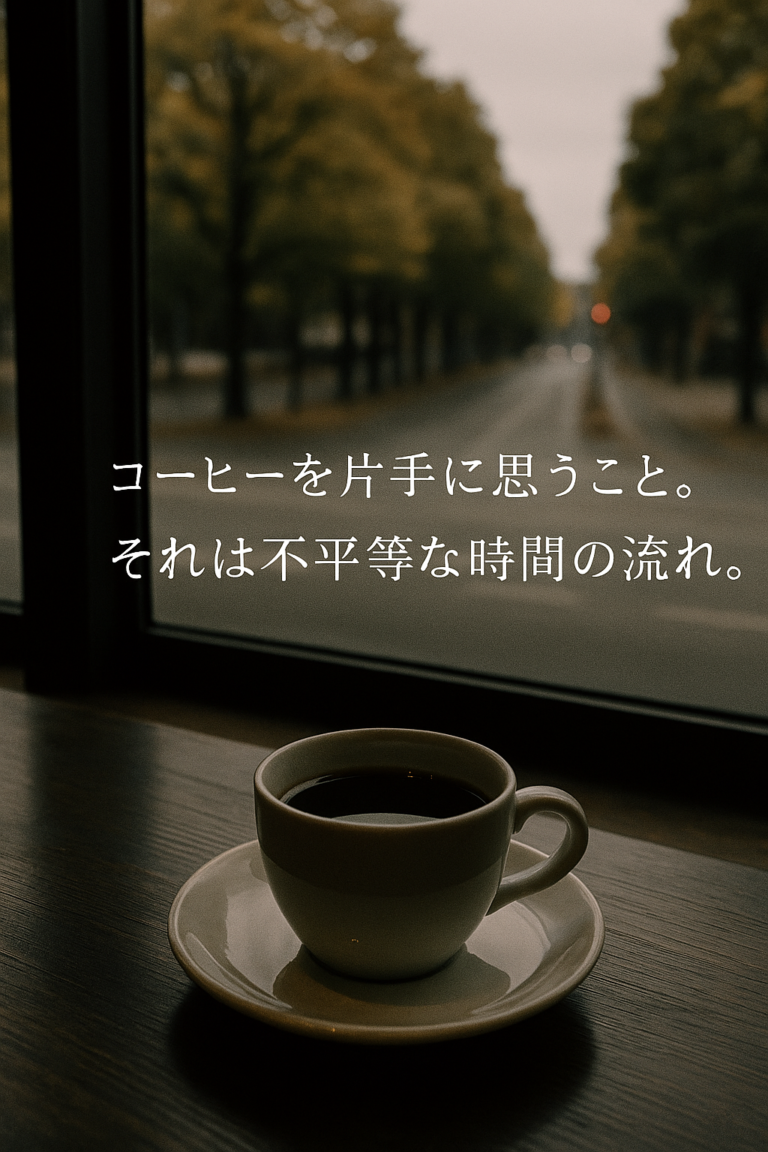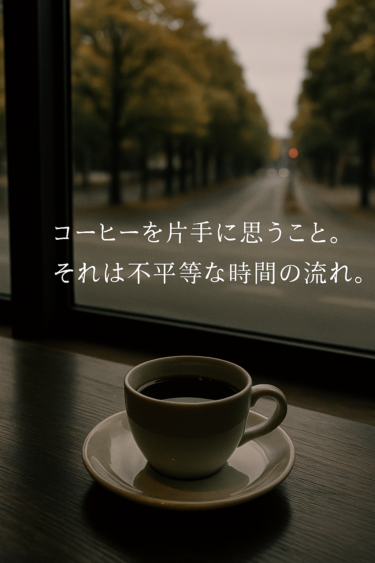──音無 Fade
コーヒーを片手に思う。
時間は、いつも不平等だ。
進むときはあっという間で、
止まったように感じるときほど、
何も変わらず過ぎ去っていく。
–
「よかったじゃないか」
――あの声が、ふと耳の奥でこだまする。
そう、あのとき誰かがそう言ってくれた気がする。
「君もようやく“普通”の生活に戻れたんだ」って。
それが祝福だったのか、慰めだったのか、今でもわからない。
–
私は“普通”に戻ったのだろうか。
あれほどまでに渇望していた“まともな日々”に。
それとも、ただ慣れただけなのだろうか。
コーヒーの表面に、空の光が揺れている。
静かな店内。冷めたカップ。
でも、どこかに確かに温度は残っていた。
–
「これまでの自分を全部捨てて、
それでやっと普通になれた――なんて、ちょっと違和感があるんです」
そんなことを、誰かに言った記憶がある。
でも、その“誰か”の顔が、もう曖昧だ。
探していたものは、ずっと前に見つかっていたのかもしれない。
いや、ただ私が気づかなかっただけか。
あるいは、見つけたくなかったのかもしれない。
–
見つけてしまえば、終わってしまう気がしたから。
その“何か”を探している限り、私は何者かでいられると思っていた。
でも、そんな逃げ道も、今はもう見えなくなってきている。
–
昼の喫茶店で、音楽がゆるやかに流れている。
スプーンの音。カップを置く微かな響き。
それが、自分の存在を証明してくれるようで少しだけ安心する。
–
窓の外、街路樹の葉が色づきはじめていた。
強い日差しのわりに風が冷たい。
本来なら、この季節がいちばん好きなはずだった。
だけど今は、
好きだったはずのものにも、少し距離を感じる。
–
「最後まで聞いてみることにするよ」
また声が、記憶の中から浮かんでくる。
聞いてほしかった言葉。
でも誰にも話せなかった話。
だから私は今、こうして一人で思い返している。
–
秋の陽が、車窓のガラスを斜めに照らしていた。
もし、あの人に会う前にこの景色を見ていたら、
私はもっと違う答えを出せていただろうか。
今さら考えても仕方のないことばかりが、心の中で渦を巻く。
–
ドライブの途中で、車を停めた。
エンジンの音が消えると、
季節の静けさがそのまま耳に染み込んでくる。
窓を少し開けてみる。
冷たい風。乾いた匂い。
胸の奥に沈んでいた何かが、わずかに揺れた。
–
私は目を閉じて、静かに呼吸を整える。
それだけで少しだけ、自分を取り戻せた気がした。
「……あの話の続きは、また今度にしようか」
口に出さず、心の中でそうつぶやく。
–
そう、話の続きを誰かと分かち合う日は、
きっとまだ、どこかにあるはずだから。
少しずつ薄れていく季節の中、
私はありったけの笑顔で、
それでも前を向いてみることにした。