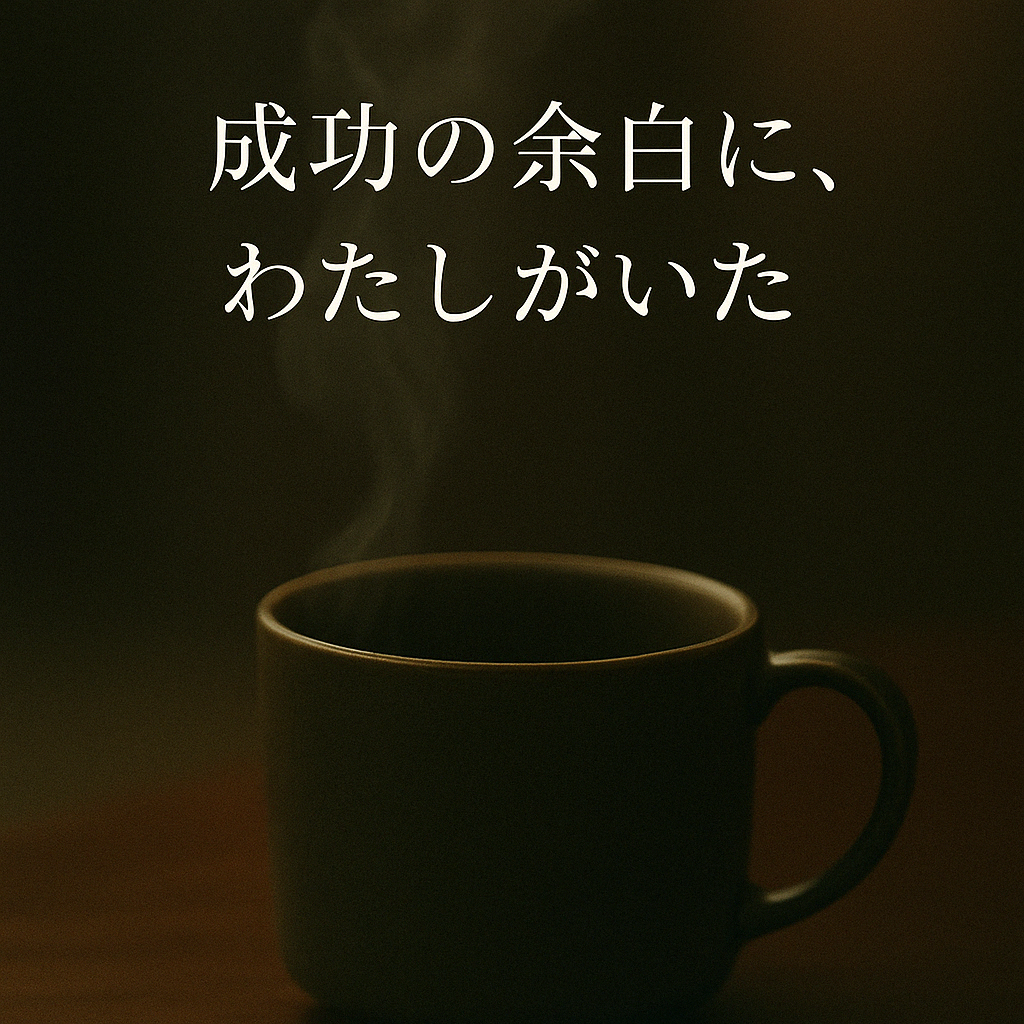「溶けかけた午後に」
コンビニの袋をぶら下げて
ぬるくなった炭酸水を飲む。
舌の奥が、わずかに泡立つだけで、
何も刺激は残らない。
冷房の効きすぎたタクシーのシートが
シャツの背中を濡らす。
汗か、湿気か、もう判別できない。
ただ、呼吸だけがやけに重たい。
信号待ちで隣に停まったバイクから、
焦げたマフラー音と
フローラル系の柔軟剤が混ざった風が流れてくる。
その香りが、なぜか誰かの家の記憶を連れてきた。
誰のだったかは思い出せない。
思い出す気もない。
スマホには通知が三つ。
誰かが何かを伝えようとしてる。
でもその“誰か”も“何か”も、
もうしばらく、
自分とは関係のない言語であってほしいと思った。
誰かを好きになったわけじゃない。
何かを失ったわけでもない。
ただ今日は、
気温も、時間も、自分も、
すべてが限りなく“夏”に近い梅雨の時期だった。
だから、
午後はそっと、溶けるように終わっていった。