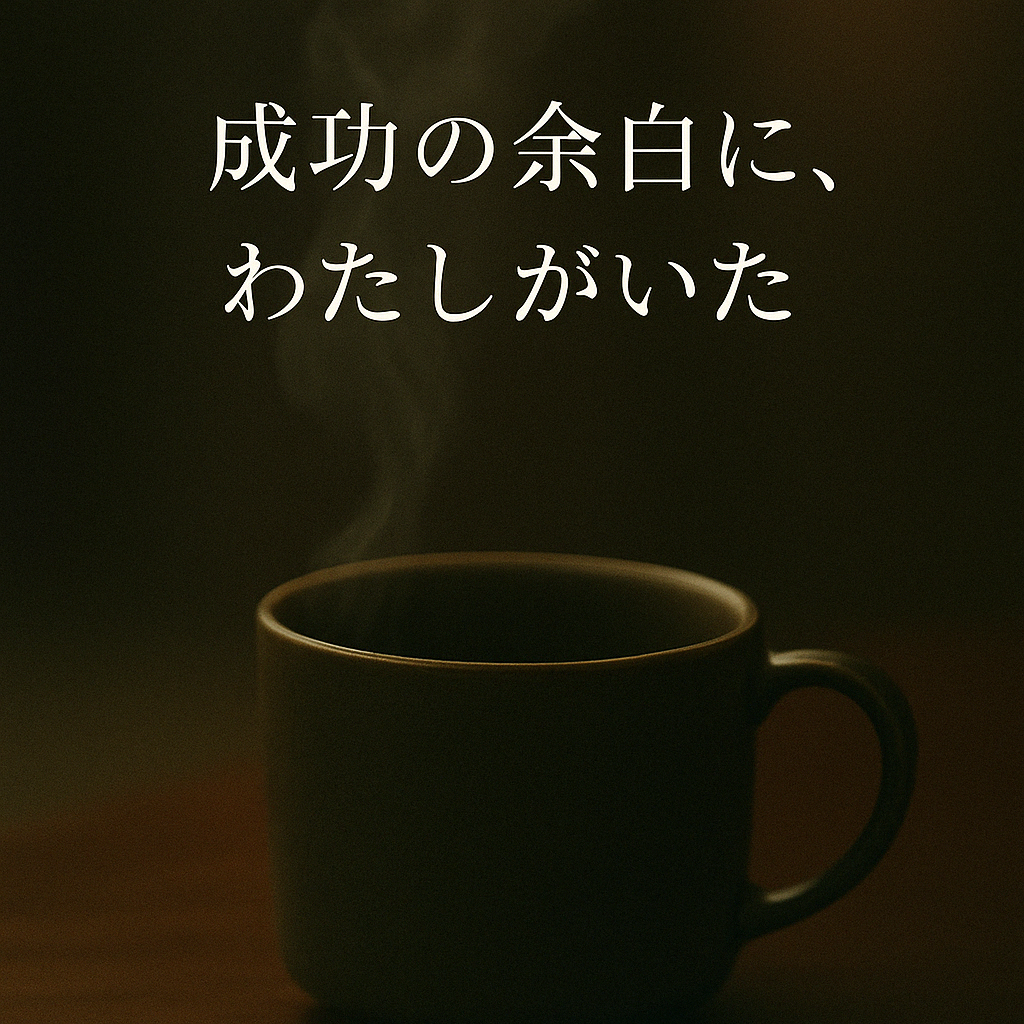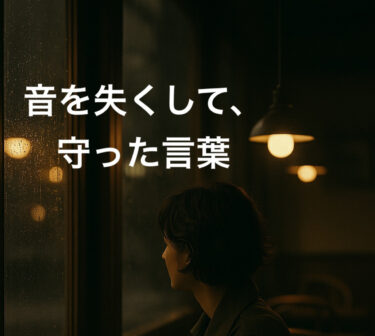──音無 Fade
懐かしさは、罪に似ている。
あるいは罪か。
触れた瞬間に、もう戻れなくなる。
懐かしさは、記憶に溶けた毒。
甘くて、やさしくて、だけど決して無害ではない。
–
久しぶりに降りた、終点間近の小さな駅。
錆びた駅名標が変わらずにそこにあったことに、
少しだけ安堵してしまう自分がいた。
足元には濡れた落ち葉、
空気は冷えていて、懐かしさと後悔が入り混じる匂いがした。
通りの向こうに、まだ灯りがついているのが見える。
あの喫茶店――「オルフェ」
もう閉店しているはずだと思っていたのに、
扉はゆっくりと開いた。
–
店内のレイアウトは、
あの頃とまったく変わっていなかった。
そして、
カウンターの奥にいたのは、間違いなく彼女だった。
灯子(とうこ)。
–
彼女は僕に気づいても、何も言わなかった。
ただ、棚からカップを一つ取り出し、
コトリと音を立てて置いた。
言葉はなくても、
あの頃の空気だけが、ゆっくりと戻ってくる。
–
「ここ、まだやってたんだな」
僕の声は、少しだけ震えていたかもしれない。
灯子は笑った。
そして言った。
「やめる理由も、続ける理由も、同じくらい曖昧だったのよ。
あなただけが、はっきりしてた」
–
僕たちは一度、
触れてはいけないものに触れてしまった。
恋ではなかった。
愛でもなかった。
ただ、日常の綻びの中にあった、一瞬の逃げ場。
あれは過ちだったのか。
それとも、必要な毒だったのか。
–
「この味、変わらないね」
「変えなかったのよ。…誰かが、また飲みに来る気がして」
–
その夜、僕は駅には戻らなかった。
店を出て、二人で歩いた。
名前のない交差点。
風の音だけがしていた。
–
僕は思った。
この記憶はきっと、
またいつか自分を苦しめるだろう。
それでも。
それでもいまは、
この罪のような懐かしさに、
少しだけ甘えていたかった。