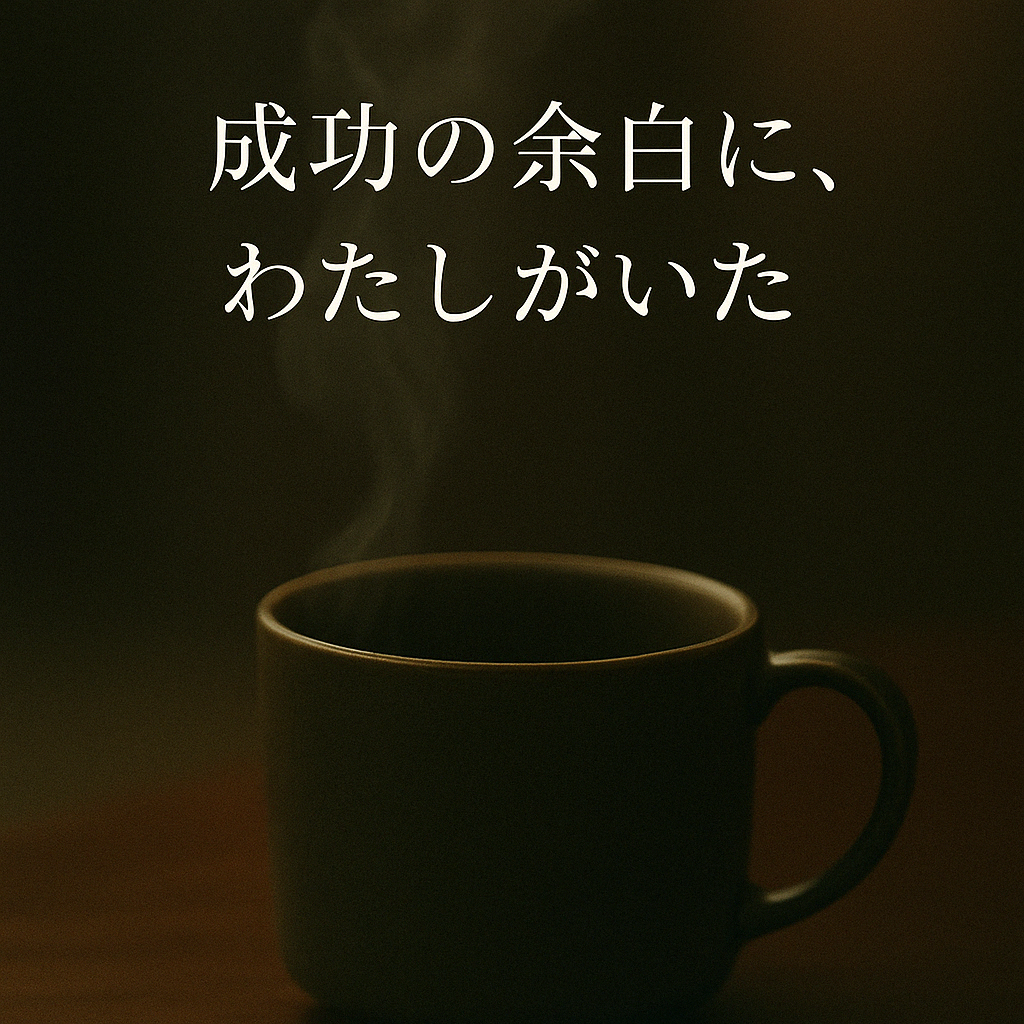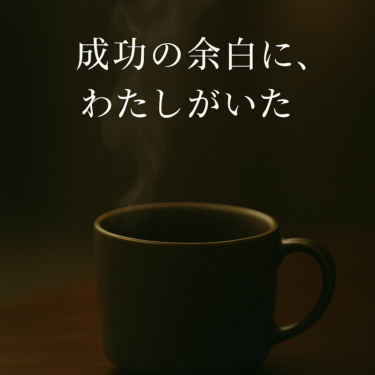──音無 Fade
一杯のコーヒーを淹れる姿は、
まるで何かを祈るようだった。
あるいは、ささやかな願い事。
湯気の向こう、何気なく窓の外を見る。
銀杏の葉がひとつ、静かに落ちていった。
限りなく冬に近い秋が、
昔からいちばん好きだった。
誰かを失くしたあとでもなく、
何かが始まる手前でもない。
すべてが、そっと止まっている感じがして。
–
店の名前はなかった。
扉の前に立っても、ここが店なのかどうかさえわからない。
でも、この場所を知っている人は、
まるで引き寄せられるように、
ふと立ち止まり、扉を開けてしまう。
中には数脚の椅子と、静かな空気。
時間の外に置かれたような古びた空間。
そこにいる男は、何も聞かない。
何も語らない。
ただ一杯のコーヒーを、祈るように淹れている。
–
私がここに来たのは、三度目だった。
一度目は、声を出さずに席に座り、
二度目は、なにも頼まずに出ていった。
三度目の今日は、
やっとカップに指をかけることができた。
–
窓の外に広がるのは、
音のない町の景色。
色を失くしかけた木々と、
誰も渡らない横断歩道。
その景色に似ていた。
私が言えなかった、たった一言に。
「ありがとう」とも、「ごめんね」とも言えず、
置き去りにしてしまった誰かの記憶。
–
カップを口に運ぶと、
その香りと温度に、
胸の奥で凍っていた何かが、わずかに動いた気がした。
声にはならないけれど、
小さく、心の中で言ってみる。
「元気でいてくれたら、それだけでいい」
–
限りなく冬に近い秋が好きなのは、
たぶん、そういう感情を誰にも見つからずに
そっと思い出せるからだ。
–
今日もまた、
誰にも届かないままの祈りが、
この場所で湯気になって昇っていく。
静かで、あたたかくて、
少しだけ、苦かった。