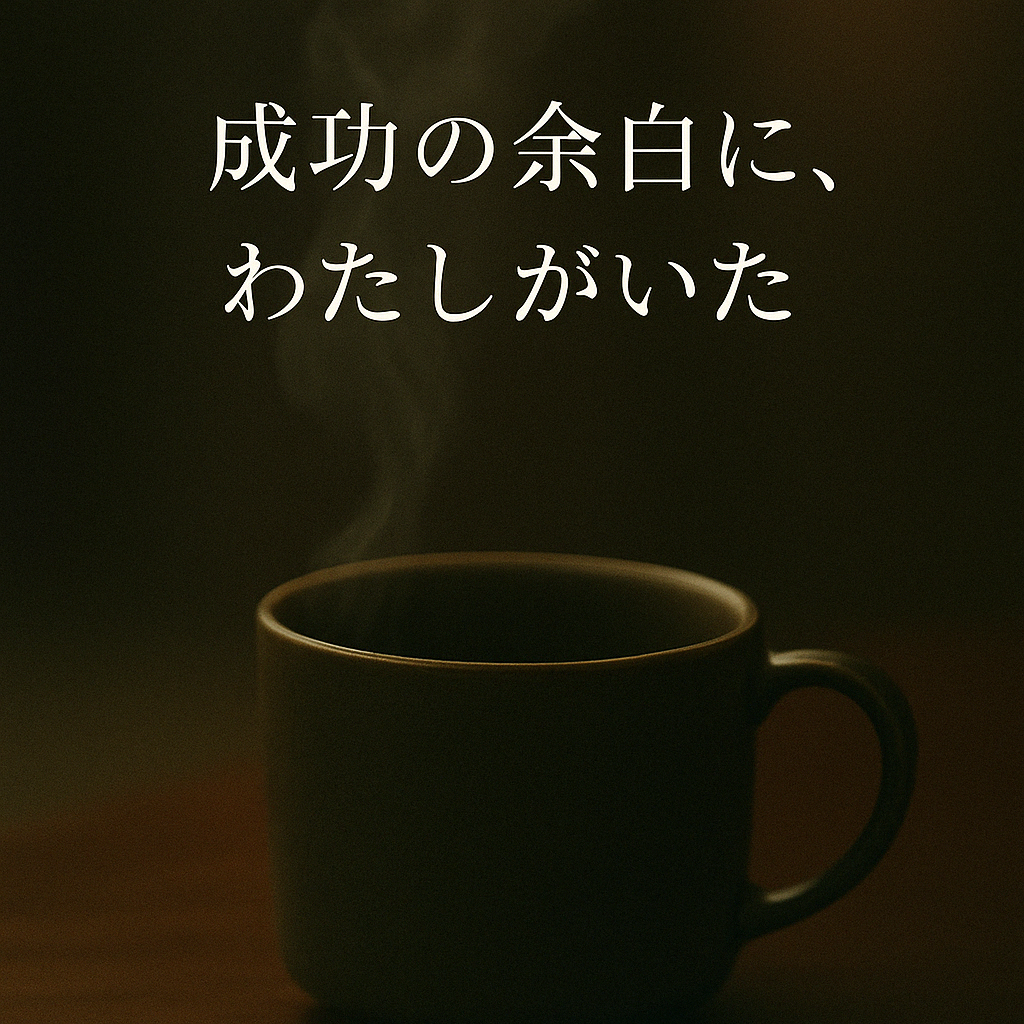──音無 Fade
「普段ならチェーンでいいけれど、仕事のお話する時はちゃんとした喫茶店に入る事にしているの」
そう言って、彼女はブラックのコーヒーに口をつけた。
苦味のあとに一瞬だけ眉を寄せて、すぐ何事もなかったような顔に戻る。
私はその仕草に、ひどく見惚れていた。
–
年上の女性というより、“大人”という印象だった。
職業も肩書きも、どこか遠くのものに思えたのに、
彼女はなぜか、
この喫茶店という限られた空間だけでは、すぐ隣にいた。
–
「君は何を飲むの?」
そう聞かれて、私は反射的にカフェオレを頼んでいた。
ブラック、と言えなかった自分が少しだけ悔しかった。
–
彼女は名刺を置くでもなく、ビジネスの話に入るでもなく、
ただカップを指でゆっくり回していた。
それが彼女にとっての“間”なのだと、私は気づいた。
「今日はお話、というより……少し空気を知りたかったの」
–
“空気”
彼女が言うと、ただの言葉が、
特別な意味を持つように聞こえる。
–
話は取りとめもなく続いた。
仕事のこと、東京のこと、喫茶店のこと。
彼女がときおり見せる微笑は、
どこか、懐かしさを含んでいた。
–
私はこの空気の中で、
ずっと年齢の違いを感じていた。
でも、それは数字のことじゃなかった。
人生の重なり方とか、
傷の数とか、
そういう“温度”の違い。
–
「あなたって、きっと無理しちゃうタイプね」
不意にそう言われて、言葉に詰まった。
図星だったから。
–
「でも、そういう人の方が、実は柔らかくていいと思うのよ。
カチカチな人って、自分が壊れる音も聞こえないでしょ」
彼女の声は、カップの向こうからゆっくりと届いた。
–
会計を済ませて、外に出る。
夕方の街に風が吹いていた。
「じゃあ、また」
そう言って彼女は去っていった。
足取りは軽いのに、なぜか背中が遠く見えた。
–
私はスマホのカレンダーに、
今日の日付をそっとマークした。
「仕事の話」なんて、きっと最初から口実だった。
–
次に会える保証なんてないけれど。
たぶん私は、
彼女が飲んでいたコーヒーの味を、
ずっと覚えていようとするのだと思う。